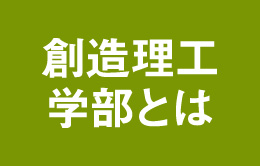
現代の複雑化した社会問題を、
幅広い視野を持って解決する、
真のリーダーの育成を目指す。
| 創造理工学部長・研究科長 環境資源工学科 | |
| 所 千晴 教授 | |
| Chiharu TOKORO, Professor Department of Resources and Environmental Engineering | |
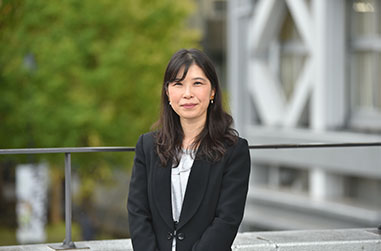
Q 創造理工学部の教育の特徴を教えてください。
1908年、早稲田大学が理工科(理工学部の前身)を設置するにあたって最初に機械、採鉱、電気、土木、建築、応用化学という6学科の新設を決めたのですが、創造理工の5学科はこれら当初から構想されていた学科にオリジナルがあります。創設者の大隈重信が構想した、理学と工学が融合した新しい形を体現しているのが創造理工学部なのです。
具体的には実学を重視し、「人間」「生活」「環境」に関係する分野を対象に、社会実装を重視した教育を展開しています。実学とは、現代社会の複雑で多様な課題に、現実的に役に立つ学問のこと。さらに、革新的でありながら、持続可能な解決策を見出すことが私たちの使命です。
Q 創造理工学部の優位性はどのような点でしょうか。
理工学部全体の話になりますが、私立大学のなかで都心にこれだけの規模の理工系キャンパスを設置している大学は、あまりないでしょう。土地や設備など、さまざまな点で大きな力が必要となり、簡単なことではありませんが、情報や人材が集まってくる東京の中心にあることは、大きな魅力と言えるでしょう。
そんな理工の中でも、創造理工学部には現代社会の基盤となる建築、総合機械、経営システム、社会環境、環境資源という分野が揃っています。歴史があり、経済活動に直結する分野であるというのも特徴の一つです。
また、文系の教員で構成される「社会文化領域」が設置されているのですが、ここでは語学教育はもちろん、コミュニケーションや合意形成の技術など、大学生―ひいては研究者―に求められる必須の素養を学ぶことができます。
国際的な教育にも力をいれていて、SHIPという英語学位プログラムで2つのメジャーが設置されています。ただ、英語で教育をするということだけではなく、日本の文化や言葉も学んで4年次には通常の日本語プログラムを受けている学生と一緒に研究することを大切にしています。さまざまなバックラウンドを持った仲間と接することは、大変な面もありますが、人間のスケールを大きくします。これは問題解決能力にも直結するはずです。
理工系以外の幅広い分野の知識と理解も必要

Q どのような人材を輩出していきたいと考えていますか?
私たちは、現代の多様で複雑な社会の課題を解決できるグローバルリーダーの育成を目指しています。リーダーとなるには、まず理工系の深い知識を身につけることが必要です。そのために、入学時から学科を選択してもらい、専門教育を行っています。
その上で、リーダーとしての素養を幅広く習得し、プレゼンテーションや文章表現を養うための「創造理工リテラシー」や、これらのスキルを用いて問題解決の課題に企業からの講師と共に取り組む「共創ワークショップ演習」といった特色のあるプログラムを展開。さらに、留学や企業との共同研究にも力を入れています。
Q 企業と関わる機会は多いのですか?
例えば共創ワークショップ演習では、日本を代表する企業の方に講師をしていただいています。そこで提供される実践的な課題に取り組むことで、キャリアパスがイメージしやすくなるでしょう。また、研究室に入ってからは、企業との共同研究を通して、自分のやりたいことや進みたい道が、より明確になっていきます。
博士号を取ってから、企業に就職する学生も増えてきています。
以前は、博士号取得後のキャリアパスは、アカデミックポストを目指すというのが一般的なイメージでしたが、それは昔の話。理工系の技術が必要とされる課題を、プロジェクトベースで問題解決に貢献できる博士人材は、今や企業からも引く手数多です。
そこで、博士人材のために、W-SPRINGというプログラムを早稲田全学で取り組んでいます。これは博士学生に最長3年間の資金援助と、学位取得後のキャリアを見すえたカリキュラムに基づく育成コンテンツを提供します。これは、博士人材が社会で幅広く活躍するための素養を身に付けながら、研究に専念できるように支援するためのものです。
「世の中をよい方向に変えたい」という強い思いを
Q 創造理工学部の学生にどのようなことを期待しますか?
創造理工の目的は、「人間」「生活」「環境」の視点で社会問題を解決することですが、これには、多角的な知識や視野が大切なので、専門や技術に関わることだけでなく、社会や政治、世の中の仕組みなど、どんなことにも興味をもってほしいですね。
私の専門はサーキュラーエコノミーですが、地球環境のことだけを重視すれば、経済の停滞に繋がりかねない。「サーキュラー=循環」とは、まさにバランスをとることなのです。問題解決も同じように、バランスをとることが不可欠。もはや自分の専門だけを考えていれば良いという時代は終わっていますから、さまざまな分野との共創や協働を通じて、バランスをとっていかなくてはならなりません。
そんなときに一番大切なのは、好奇心を持つこと。好奇心のままに、さまざまな分野に健全な興味を持つことが、コラボレーションを円滑に進める力となります。これから進学する皆さんにとっては、勉強や研究で行き詰まったときにも、好奇心は役に立つはず。「なぜ、そうなるのか」「思ったとおりにならないのはなぜか」と考えることが、そうした壁を乗り越える原動力になります。
そして、創造理工学部の学生には、「世の中をもっとよくしたい」という強い思いを持って、研究に挑んでほしい。真のリーダーになるために必要な素養であるからです。大きな希望を持って、進学してきてください。

