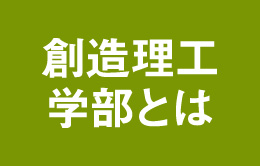学部長賞受賞作品
これから、**グループのプレゼンテーションを始めます。私たちの班は「藻から作るバイオ燃料」をテーマにしました。現在、次世代エネルギーとしてバイオ燃料が注目されていますが、その中でも藻類から作るバイオ燃料が有力視され、研究も盛んに行われています。今回はその概要を紹介したいと思います。
はじめに、エネルギー問題の現状について、簡単に見ると、まずは地球温暖化問題が挙げられます。二酸化炭素を出さないエネルギー生産が求められています。また、石油の枯渇も危惧されます。石油の可採残存量は約40年分とも言われています。そして震災の原発事故により、代替エネルギーを求める声も大きくなっています。このような背景から、現在、再生エネルギーの需要が非常に高いのです。
その再生可能エネルギーとして注目されているのが、バイオ燃料です。そのメリットを見てみましょう。まず一つ目のメリットは、永続的な生産ができることです。石油のように枯渇しません。また「カーボンニュートラル」であることも重要です。下の図を見てください。光合成でCO2は植物に吸収され、その植物を燃料にして、燃焼することでまたCO2が出ます。このとき地球上の総炭素量は変化しないことがわかります。これがカーボンニュートラルです。このようにバイオ燃料は多くの長所をもちます。
しかし悪い面もたくさんあります。この図はバイオ燃料のデメリットを端的に表しています。
バイオ燃料の原料は現在、とうもろこし、サトウキビなどが使われています。したがってその分食料が不足してしまう危険性があります。実際、世界の石油需要50億トンをすべて、とうもろこしのバイオエタノールでまかなうと、今ある耕作地の14倍は必要です。また新たに耕作地を作って森林を伐採すると、逆にCO2を増やすことになります。このように、環境に良いバイオ燃料も、大きな問題点を抱えています。
これらの問題点を解消するのが「藻」です。藻類の中には、石油に似た成分を蓄積する種類が存在します。それが現在、バイオ燃料の有力候補になっているのです。先ほど挙げたバイオ燃料の問題点に対して、藻は、食料と競合しない、抜群にオイルの生産効率が高い、などの特徴を持ち、バイオ燃料のデメリットをカバーすることができます。
有力とされるのが「ボトリオコッカス」という種類の藻です。この藻は光合成で石油を作ります。しかし生産コストが非常に大きく、自動車燃料を作ると1リットルあたり150円から800円となってしまい、実用化はまだまだ難しいとされていました。
そのような状況で、2010年に「オーランチオキトリウム」という種類の株が見つかりました。「ボトリオコッカス」に比べ、なんと10から12倍の生産効率をもっています。これにより実用化の展望も大きく開けました。「オーランチオキトリウム」は、光合成をせず、有機物を食べてエネルギーを得ます。そのため、日光を必要とせず、深い水槽の小さいスペースでも生産できます。さらに排水の有機物を食べさせ、下水処理しつつ石油を生産する、という構想も考えられています。「ボトリオコッカス」と組み合わせてさらに生産性を高めれば、将来的には自動車燃料も1リットルあたり50円になります。試算によると、335,000[ha]の生産施設で、日本の輸入量の石油を作れます。日本の休耕地が620,000[ha]であることを考えると、日本が産油国になることも夢ではないかもしれません。
今説明した、「石油を作る藻」は夢のようなエネルギーですが、まだまだ課題は多く、少なくとも実用化まで10年かかるといわれています。しかし実用化すれば、今あるエネルギー問題のほとんどが解決されます。それぞれの国が自前でエネルギーを作ることができれば、国が豊かになり、石油を巡るような争いもなくなり、真の世界平和が実現できると考えます。藻のバイオ燃料の研究のいち早い実用化を期待したいです。
以上で**グループの発表を終わります。
一覧へ戻る