
「人間とは何か」を考え、
歴史に「知」を編み込む——
実践と理論を行き来する、幅広い工学
| 総合機械工学科 教授 | |
| 上杉 繁 | Wesugi Shigeru |
| 専攻分野 ヒューマン・インタフェース工学、デザイン工学 2024年度インタビュー | |

研究対象は「人間と技術の関係」
道具や経験をデザインする
一般的に、学問はそれぞれに体系があります。工学を学ぶ際にはその体系において、何かをつくるための専門性を身につけていきます。ヒューマン・インタフェース工学をはじめ、人間と技術の関係を扱う領域は、人間に関する現象を対象とするため、学問としての枠組みがとても広いことが特徴です。特に私は、機械工学を基盤とし、「システム論」「道具論」「拡張論」などを組み合わせながら教育と研究を進めています。
人間と技術の関係を扱う学問領域はさらに展開しており、実践と理論を行き来きしながら取り組んでいます。その中で、私の研究室では、人間の経験を「つくる」「つたえる」「つながる」という切り口を用意し、道具やデザインの研究につなげています。
もう少し説明しますと「道具を使用することで新たな身体動作や行為を創出するデザイン」、「感覚やイメージなどを共有・伝達する方法のデザイン」、「身体活動の活性化を介した自身の身体や他者とのかかわり方のデザイン」のように、概念段階から具体的な装置、社会における活用までも含むテーマに取り組んでいます。
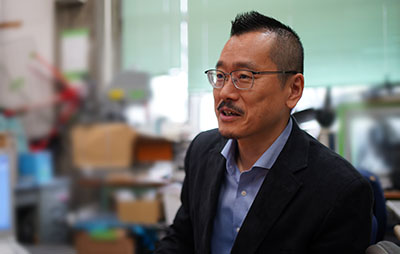
これまでは扱いきれなかった
「人間にまつわる問題」を紐解く
近年の研究事例としては、「運動の負担を軽減するテンセグリティスーツの開発」「運動のコツを探索して身につける手助けをする方法・装置の開発」があります。
「運動の負担を軽減するテンセグリティスーツ」は、人間の筋肉や腱、骨のつながりを模した「テンセグリティ構造体」を下肢につけることで、歩行器の代わりを目指す道具です。「テンセグリティ構造体」には、大きな力を加えても壊れずに変形し、力を戻すと元の形に戻るような興味深い性質があります。張力を使ったこの構造を利用して、ロボットスーツよりも手軽で歩行器よりも幅広い動作を可能とする、新しい装具の開発を目指しています。
「運動のコツを探索して身につける手助けをする方法・装置の開発」は、例えば、怪我しにくい走行フォームを、走りながら身につけられる装置を開発しています。装置の体に当たる側に振動装置が入っています。走行中、走者が怪我しにくいフォームへ近づくように、その部分の装置が振動します。走者は、体をなぞられているような錯覚を体験し、フォームをどう修正すべきか分かるのです。
このように私の研究室では、人間の経験を拡げる道具のデザインを、幅広く扱っています。その分、伝統的な機械工学では扱いきれなかった問題をテーマにすることも多く、何を手掛かりに取り組むべきか悩むこともあります。だからこそ、手掛かりが見つかった時には突然目の前が開けるような爽快感があり、喜びとやりがいを感じますね。

テンセグリティ構造体の一部
どこへ行っても親しまれる
他にない研究に打ち込めるのが早稲田
総合機械工学科の全ての研究室に共通するのは、「人間・社会・環境など、現実社会と直接つながり、貢献する」という点です。よりよい社会の実現へと向かうため、問題解決や価値の創造を目指す。その姿勢は、早稲田キャンパス内に記念博物館がある會津八一(あいづ・やいち)が唱える「実物尊重の学風」に通じます。
時に「人間とは何か」を根本から考えて問題に取り組む、人間の存在そのものを問う姿勢は、一見、実学から遠い印象です。しかし、長い歴史の中で見ると、現在から未来へと地続きになっている姿勢なのです。産業への貢献のみならず、人間の歴史に何かしら貢献できる「知」をいかに残すか。それが私たちの役割だと考えています。
また、早稲田のよいところは「教員と学生の距離が近く、一緒に問題解決に取り組めること」「ものづくりプログラムや起業支援など、挑戦できる環境が豊富なこと」です。特に本学ならではだと感じるのは、「全国どこへ行っても、好意的に受け入れられること」。一目置かれる感じがある反面、庶民的な親しみやすさもある。海外で日本に関係のある人と出会ったとときも、早稲田の名前を出すと「おお!」と反応があります。より偏差値の高い大学もありますが、これほどの知名度と親しみやすさがある早稲田は、やはり独特な存在ではないでしょうか。
早稲田を目指す皆さんには、ぜひ早稲田でしかできないことに挑戦してみてほしいです。私自身も同じことを思い、就職後に大学院に戻って研究を始めました。直ちに解決してしまう課題ではなく、時間をかけて取り組む必要があるテーマだからこそ、粘り強く挑戦できます。そのためにも、先入観にとらわれず、社会に対してさまざまな視点から関心を持ってほしいです。
今後の展望としては、「人間と技術の関係を考える学問領域を体系化したい」という目標があります。切り口や方法を整え、体系化された学問として扱えるようにしていきたいです。會津八一が言及した「学匠」への憧れもあるので、研究者や学者とも一味違う、「学問の匠」へと近づいていきたいですね。

