
建築学専攻
総合機械工学専攻
経営システム工学専攻
建設工学専攻
地球・環境資源理工学専攻
「土×3Dプリンティング」という
新たな建築材料に着目
| 建築学専攻 修士2年 | |
| 兵頭 なつみ | Hyodo Natsumi |
| 輿石直幸研究室 2024年度インタビュー | |

期待の建築材料「土」
その有用性を証明したい
Q. 修士論文のテーマはどのような内容ですか。
「土素材を活用した建設3Dプリンティング材料の調合決定手法に関する研究」です。輿石研究室は建築材料を取り扱っており、私はその中でも「土」を修論のテーマにしました。広島県産の真砂土(まさど)を材料として、3Dプリンティングで建物を造る際に、水や固化材の割合などの調合を決定するための仕組みを研究しました。
建築に使う3Dプリンターはかなり大きく、クレーンなどの先端にノズルをつけて、ポンプで材料をノズルへと送る仕組みです。その際、土が硬すぎるとノズルまで送れず、軟らかすぎるとプリンティングの途中で崩壊してしまいます。ちょうどよい軟らかさ、かつ硬化後の性能も備えている調合を探し、実験を重ねました。
実験では、土に水や酸化マグネシウムをさまざまな割合で混合し、その材料をポンプで圧送して負荷を測定したり、強度を確認したりしました。ある設計事務所からのご要望を受けて、ワラを混ぜ込んだ実験なども行っています。
最終的には、「実際にプリントしてみよう」という直前まで研究が進みました。ゼミの後輩が研究を引き継いでくれるので、卒業後も研究のお手伝いをしたいと考えています。
Q. 卒論でも同じテーマで研究されていたそうですね。土をテーマに選んだ理由を教えてください。
研究室を選ぶ際に見せていただいた、土の建築に関する本がきっかけです。その本は先生が翻訳した海外の書籍で、そこで初めて「海外建築での土の使われ方」に触れました。「土の建築って成り立つんだ」「日本でも工夫すればできるかも」と、土に興味を持ったんです。
建設分野は資源消費量・廃棄物量がともに多く、建築資材の供給は非常に不安定です。その点、土は解体後も大地に還るので環境への負荷が少ないですし、枯渇する心配が少なく、世界各地で調達することが可能です。成形もしやすく、期待されている材料なんです。
地震や災害が多い日本では、土はまだ建築資材として活用されていません。だからこそ、研究を通して「地震や災害に耐えられる建築物は、土でも造れる可能性がある」と知ってほしかったんです。
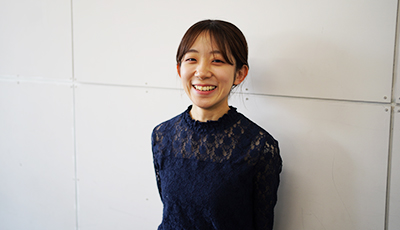
研究と一対一で向き合えるのが、輿石研究室の強み
Q. 早稲田の建築学科の良さは、どんなところですか?
課題を通してたくさん手を動かせますし、先生や同級生との意見交換を通して、視野がかなり広がるところです。才能があって尊敬できる同級生たちと、熱意をもって取り組んだ課題を共有できますし、時間と労力をかけるほど考えが深まります。
模型や図面を書くなど、アウトプットを要求される機会が多いので、表現力も鍛えられると思います。限られた条件の中で、自分の考えをどう表現していくか。その一方で、図面トレースのようなシンプルな作業に、時間をかけて丁寧に向き合うこともできる環境です。
Q. 輿石研究室のいいところは、どんなところですか?
それぞれが自分のペースで集中して、黙々と研究に取り組めるところです。コアタイムもないですし、先生の方からどんどん指示が出るわけでもありません。研究と一対一で向き合える環境が、輿石研究室の強みだと思います。
その分、自分で計画を立てて行動を起こしていく必要はありますが、行動するほどいい研究ができる実感がありました。先生とのゼミでは、自分では気が付かない部分まで丁寧に見ていただけるので発見が多いですし、同級生たちも、相談すると親身になって聞いてくれます。そうして気付きを積み重ね、研究との向き合い方を少しずつアップデートできる感覚がありました。
文章表現についても、かなりしっかり教えてくださいます。先生は「正しく分かりやすく伝える」ということを大切にされています。研究で成果を出しても、社会に伝わらなければ自己満足になってしまうからです。「社会に対して、研究の意義や貢献度をしっかりと伝える」という教えは、今も糧になっています。
材料や土地と向き合い、人に長く愛される建物に
Q. 今後の展望について教えてください。
4月からは、某組織の建築設備に関わる仕事に就きます。運営管理する建物が全国にあるので、それぞれの土地に合った建物を考えつつ、丁寧につくっていけるのは貴重な機会ですよね。日本の材料や建物、土地のことをもっと知りたいので、とても楽しみです。
今の建築生産の仕組みでは、一つひとつの建築に向き合いそれぞれに個性を持たせるのは、なかなか難しいことだと思います。それでも、個性を持たせて人に長く愛される建物にすることこそ、今後大事になると考えています。私はそこに向き合っていきたいです。

