
建築学専攻
総合機械工学専攻
経営システム工学専攻
建設工学専攻
地球・環境資源理工学専攻
数学的アプローチで「なんとなく」に定量的な根拠を
——ファストパスの効果をシミュレーションで分析
| 経営システム工学専攻 修士2年 | |
| 石井 友梨 | Ishii Yuri |
| 蓮池研究室 2024年度インタビュー | |
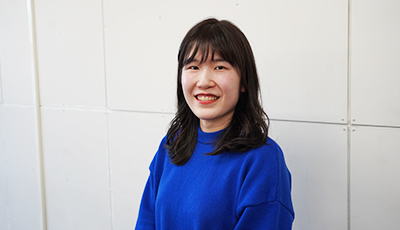
待ち時間を最適化する優先搭乗パスのあり方を分析
Q. 現在取り組んでいる研究の内容について教えてください。
修士論文のテーマは「テーマパークにおける新しいアトラクションの優先搭乗パスの配布方法の分析」です。これについて、オペレーションズリサーチの最適化シミュレーションという手法でアプローチしました。
オペレーションズリサーチは、複雑な問題に対して、数学や統計学の手法を用いて解決を試みるもので、「この状況ではなにが最適な選択か」を導き出す手法です。なかでも、私は数学的モデリングや統計分析を活用する、最適化シミュレーションという方法を採用しました。
具体的には、テーマパーク運営の視点に立ち、新しいアトラクションの優先登場パスを配布する際に、混雑分散や顧客満足度、待ち時間の最適化にどのように影響するのか、検証しています。たとえば、ディズニーランドのファストパスの価格設定や購入率に対して、どの程度の顧客が利用したかを示すサービス率(回転率)や、顧客満足度などとの関連を分析しました。
シミュレーションの結果、サービス率が高いと多くの人がアトラクションに乗れることで満足度が向上するとともに、待ち時間も軽減できることがわかりました。また、価格の妥当性についても分析した結果、価格が高くなると待ち時間は減る一方、優先搭乗パスを買わない人も増えることがわかりました。
こういった行列の待ち時間に関する問題は「テーマパーク問題」といわれ、多くの変数を設定する必要があり、シミュレーションを構築するまでの準備が大変です。先生のアドバイスや先行研究を参考にしながら、必要な変数について決めていきました。
「こんな感じじゃないか」という直感に、
定量的な根拠を示せる
Q. いまの研究にいたった経緯を教えてください。
私は旅行が好きなのですが、先生はそれにいまの研究のトレンドとをかけ合わせてくれて、いまの研究テーマに行き着きました。卒業論文では、京都などで問題になっているオーバーツーリズムをテーマに、観光客への情報提供と混雑緩和の関連性について扱っています。
観光客の現在地に対して、観光スポットまでの距離や滞在人数、人口密度などの情報を提供した際に、混雑緩和につながるのか、シミュレーションしました。結果的には、観光スポットまでの距離と待ち時間、混雑率の情報を与えることで、混雑緩和につながることがわかりました。
Q. 研究の面白さはどのような点にありますか?
この研究の面白いところは、数字で最適解を出せることです。直感的な「こんな感じじゃないか」という考えに対して、定量的に根拠となる数値を示せるのが魅力だと感じています。一方で、適切な解が出せず躓くこともあります。プログラミングではエラーが出て苦労することもありますが、そうした困難を乗り越えて結果がうまく出たときの達成感はとても大きいですね。
また、修士課程に進学したことで、専門性を深められました。卒業論文と比べて、修士論文では求められるレベルがまったく違います。2年間という長い時間をかけて取り組めるので、どういう研究をしたいかというところからじっくり詰めていけるのも魅力です。卒業論文では研究テーマを先輩から引き継ぐ形で取り組みましたが、修士論文ではさらに自分の関心を掘り下げて設定できました。
さらに、この2年間で2度の国際学会に参加できたのも貴重な経験でした。同じ学問を学ぶ世界中の研究者と交流でき、自分の研究分野が世界中で追究されていることを実感できる機会でしたね。

選択肢の多く自由な環境でやりたいテーマに出会う
Q. 所属している蓮池研究室の特徴について教えてください。
蓮池研究室は、自由度が高いことが特徴です。ミーティングも週1回程度と比較的少なめで、研究以外のやりたいことにもチャレンジできる環境です。実際、蓮池研究室には「公認会計士の資格を取りたい」「芸人になりたい」という夢を持つ学生や、体育会の部活に所属している学生もいます。
蓮池先生は、怒ったところを見たことがないほど、やさしくポジティブな印象です。穏やかでみんなのパパのような存在で、学生との距離も近く、みんな先生のことが大好きです。学会でマレーシアを訪れた際には、先生の誕生日会を開いたこともありました。
ゼミ選択では、やりたい明確なテーマや分野が決まっていなかったので、選択肢が多いところを重視しました。先生に相談した際に、「世の中は問題に溢れている」といわれたことが印象に残っています。
また、研究室や先生の雰囲気の良さも決め手になりました。説明会や見学で訪れた際、先生の授業も実際に受けていましたが、とてもやさしく接してくださいました。先輩方も仲が良く、研究室全体が良い雰囲気です。年2回ある合宿でも、ボードゲームやカードゲームを持ち寄って遊びながら、先生や先輩方と親睦を深められましたね。
数学的アプローチで社会課題を解決し、人々の笑顔を増やしたい
Q. 今後の展望について教えてください。
大手メーカーへの就職が決まっており、工場生産における無駄やムラをなくす仕事に携わる予定です。経営工学や生産管理の知識を活かせることに惹かれました。大学で学んできた自動車の生産ラインなどの知識や、データ分析のスキルを実践的に活用したいと考えています。
また、メーカーを志望した理由はコンサルタントのような改善の提案だけでなく、社員として実行まで携われる点に魅力を感じたからです。なかでも、有形商材を扱いたいという希望もあり、目に見える形で商品を届けられる仕事に魅力を感じています。
大学院での就職活動は忙しく、大学院の授業や研究、アルバイトも同時に進めていたため、忙しくて大変さはありました。ただ、その分計画的に動く必要があり、時間の使い方や予定のマネジメント能力が身についたと思います。
将来的には、社会的な課題や悩みごとを解決する手助けをしていきたいと考えています。人々の笑顔や幸せを増やしていくことが目標です。製品を手に取ってくれたお客様の笑顔を見ること、便利な商品で人々の手間を省けるなど、世の中の幸せを少しでも増やせたらと思っています。

