
建築学専攻
総合機械工学専攻
経営システム工学専攻
建設工学専攻
地球・環境資源理工学専攻
350年の歴史を持つ錦帯橋を守る耐久性調査
ーーさまざまな人たちとの関わりのなかで見つけたやりがい
| 社会環境工学科 学部4年 | |
| 關 日葵 | Seki Himari |
| 小野研究室 2024年度インタビュー | |
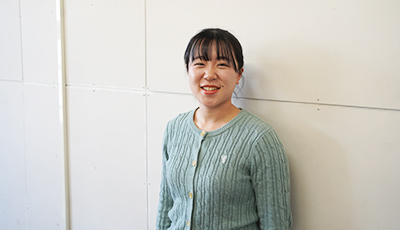
橋の歪み方や振動の仕方から耐久性を測る
Q. 現在取り組んでいる研究の内容について教えてください。
私は、橋梁の研究をしており、卒業論文では山口県岩国市にある錦帯橋の定期調査についてまとめました。錦帯橋は、1673年につくられた中央にアーチ構造を持つ珍しい橋梁で、日本三名橋にも選ばれています。
この錦帯橋の調査を小野研究室が5年に1度実施しています。調査では、橋の耐久性を確認するため、歪みの程度や振動について調べます。劣化が見られる場合には架け替えを行っており、実際20年前には新しいものに架け替えられました。
橋に振動を与える際には、現地の岩国高校の生徒さん140名に橋の上で整列してもらい、橋の歪み方を見ました。また、学生が足踏みをしたり走ったりしたときの、振動の仕方を解析し、固有振動数の範囲内にあるかどうかを確認します。調査の結果、劣化は見られるものの架替えの必要はないとわかりました。
Q. 研究の面白さはどのような点にありますか?
研究の面白いところは、さまざまな人と協力しながら取り組むところです。錦帯橋の調査でも、たくさんの高校生と関わりながら作業を進めています。また、調査前後には岩国市の方々とのやりとりをして、資料を作成したり打ち合わせに参加したりもしました。錦帯橋の調査は、大規模で責任も伴いますが、そこにやりがいを感じますね。
一方で、知識不足を痛感する場面もありました。学部の3年間は、一つの領域を極めるというよりも分野全般を勉強します。そのため、研究室に入ってから専門的な内容が増え、よくわからない単語も出てきます。4年生で研究室に入ったので、大学院に進み研究を続ければ、もっと面白いことを見つけられたのではないか、と思うこともありますね。
当たり前と思える生活の基盤を支える土木を学ぶ
Q. 社会環境工学科を選んだ経緯について教えてください。
もともと、高校生のころから物理が好きで、とくに力学の授業が印象に残っています。その授業で、厚紙とテープで紙の橋をつくって耐久性を競う実験がありました。私はトラス構造の橋を架けることで、クラスで2番目に耐久性が強い橋をつくることができました。実際に、トラスや桁橋など、どういう構造があり、それが耐久性にどう影響するのかを身をもって学んだのですが、それがきっかけで土木に関心を持ちましたね。
土木は、私たちの生活に溶け込んでいるもので、道路も鉄道も土木から成り立っています。普段は気づきにくいですが、土木によって人々の行動の幅が広がり、当たり前と思える生活の基盤をつくっています。
そうした人々の生活を支える技術に携われることが、土木の魅力です。
Q. 土木というと女子学生が少ない印象ですが、実際にはどうでしたか?
たしかに、社会環境工学科は1学年約80名のうち、女性は14人です。20人のうち4人なのは小野研究室の学生です。研究室も男子学生が多いなか、はじめは質問しづらいこともありました。ですが、先輩から声をかけてもらい、経験談や自己開示をしてくれたこともあって、その後はまったく気になりませんでした。
錦帯橋の調査でも、参加した女性は私一人だったのですが、ストレスにならないようにみんなが気を遣ってくれて、自然体でいられるようにしてくれました。土木は泥臭い印象があって女性は多くないですが、そこにハンデを感じたことはないですね。
Q. 受講して印象に残っている講義はありますか?
大学3年生のときに受講した「コンクリート実験」です。そのなかで、グループワークで鉄筋コンクリートの構造について話し合い、その構造でコンクリートの柱をつくり、強度を測る実験をしました。
私たちのグループでは、理論上ベストな配置を考え、そこから施工のしやすさも考慮しました。実際に自分たちで製作するので、誤差があっても強度を保てるようにするためです。1・2年生で机上で学んだ理論をもとに考え、実際にものをつくることで、鉄筋の構造や配置で強度の発揮の仕方が変わることを体感できました。

大学からはじめたスポーツを日々の頑張りのご褒美に
Q. 学業以外で打ち込んでいることはありますか?
大学生になってからはじめた「スカッシュ」というスポーツをやっています。スカッシュは、テニスと同じようにボールとラケットを使うのですが、四方を壁に囲まれた空間のなかで相手選手と壁打ちをしていきます。最近ではオリンピックの新種目にも採用されて注目されていますね。
スカッシュは他の選手との接触もあり、横や後ろからボールが来ることもあるので難しいのですが、勝ち方やコツが掴めてくると面白いです。また、テニスと違って大学からはじめる人が多く、自分の頑張り次第では全国大会も目指せるというのも、スカッシュを選んだ理由です。私は中高生のころソフトテニスをやっていましたが、負けて悔しい思いをした経験があるので、その挫折した経験をスカッシュで活かせたと思います。
スカッシュは文理合同のサークルに所属していたのですが、創造理工学部は研究もあり、勉強を計画的に進めねばならず、文系の学生とは忙しさが違います。そのなかで、学業のご褒美にサークル活動があるというモチベーションで、勉強を頑張りました。
自由な時間になにを選ぶか。その選択や出会いは人生の財産に
Q. 今後の展望について教えてください。
私は大学院には進学せず、ゼネコンに就職する予定です。ゼネコン勤務は現場経験が大切で、そのためにはいち早く現場で活躍したいと思い、就職を選びました。また、入社後数年は地方の現場を経験して、その後関東に帰ってくることも想定し、その時期も考えました。
ゼネコンの魅力は、大きな工事やさまざまな現場に触れられる機会があることです。現場では工事の人たちと一緒に身体を動かして取り組みますし、コミュニケーションや人とのかかわりが大切ですので、これまでの経験が活かせればと思っています。
Q. 社会環境工学科を目指す受験生にメッセージをお願いします。
大学は学ぶだけでなく、関わる人が増えるところです。高校よりも世界が広く、時間にもゆとりがあるなかで、なにに重きを置くかが大切です。その選択や人との出会い、経験が今後の人生の財産になると思います。社会環境工学科には、さまざまな世界に触れられる楽しさがありますので、ぜひ受験頑張ってください。

