
建築学専攻
総合機械工学専攻
経営システム工学専攻
建設工学専攻
地球・環境資源理工学専攻
幼いころからの関心が社会貢献の一助に
――産業廃棄物の用途開発で新たな資源循環に挑む
| 地球・環境資源理工学専攻 修士1年 | |
| 吉田 和記 | Yoshida Kazuki |
| 山﨑研究室 2024年度インタビュー | |
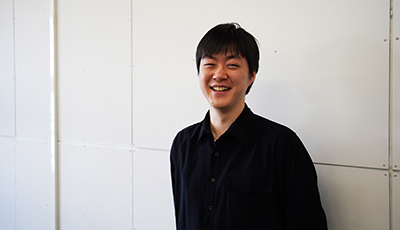
廃車両から発生する水酸化アルミニウムをジオポリマーへ
Q. 現在取り組んでいる研究の内容について教えてください。
私のテーマは、産業廃棄物を再利用した新しい建設材料であるジオポリマーです。具体的には、JRの研究機関との共同研究として、主に廃鉄道車両から取り出される水酸化アルミニウムの有効活用として再資源化するための基礎研究に取り組んでいます。
鉄道車両には、さまざまな金属が使われているため、廃車両からは様々な金属が混合されたくず鉄のような状態で廃出されます。
そのため現状、再生や転換利用用途が限られてしまっています。こうしたくず金属塊の使い道として、ジオポリマー原料への活用ができないか、検討結果をJRの研究機関と共有し、議論しながら研究を進めています。
Q. ジオポリマーとは具体的にどのような材料なのでしょうか?
一般的なコンクリートと見た目は似ていますが、原材料として主に石炭火力発電所から出るフライアッシュや高炉スラグなどの産業廃棄物を使用します。通常のコンクリートと比べて原料製造から製品作製時の環境負荷が低く、耐火性や耐酸性にも優れている点が特徴です。
モチベーションは試行錯誤した調査が社会貢献につながること
Q. 研究の面白さはどのような点にありますか?
自分の研究が将来的に社会の役に立つ可能性があることです。たとえば、先日発生した道路陥没事故では、水道管に使用されていたコンクリートの耐酸性に問題があったという指摘があります。
私が開発しているジオポリマーでは、耐酸性を向上できる可能性があり、構造材の耐久化や延命化などを付与することにより、こうした問題の解決策の1つになるかもしれません。一生懸命つくったレシピが実用に足りる結果になって、社会貢献につながればと思うと、研究のモチベーションにもつながりますね。
研究の現場では、地道な実験やデータ解析を通じて理解を深めていくプロセスが多いですが、そこから得られる達成感は非常に大きいものです。
Q. 研究を進める上で苦労された点はありますか?
廃材の水酸化アルミニウム成分によって、生成されるジオポリマーの性質が大きく変わる点に苦慮しました。当初ある箇所から供給された水酸化アルミニウムでは、強度に問題があったのですが、別の箇所から採取したものではむしろ耐久性が上がったのです。
実験では、水酸化アルミニウムにさまざまな原材料を配合してジオポリマーをつくります。2週間ほど乾燥させたあと、非破壊検査で構造を見るほか、強度の測定や組成の観察など、多角的に評価します。配合する成分の量や割合によって、養生期間を変える必要もあり、やり直すことも度々ありますね。
これまでに水酸化アルミニウム廃材をジオポリマーとして活用した例がなく、ゼロからひたすら手を動かして試験しなければなりません。そうした試行錯誤の過程で、先輩方からの助言も得ながら、適切な配合を見つけられるよう日々実験を重ねています。

幼いころから興味があった環境開発と資源循環を研究に
Q. この研究に取り組んだ背景について教えてください。
幼いころから環境や資源に関心がありました。小学生の時には、レアアースの規制が話題になり、各国で新規原料資源を探す動きがニュースになっていました。日本でも南鳥島周辺でメタンハイドレートが見つかるなど、未利用資源の可能性にわくわくしていましたね。
そうした関心から、環境と資源の両方に取り組んでいる環境資源工学科を選びました。環境開発と資源循環は、相反する性質がありますが、切っても切れない関係性にもあります。その両方の視点から学ぶことで、持続的な開発について考えられるのも、環境資源工学科の特徴です。
Q. 環境資源工学科の魅力について教えてください。
先ほどの点に加えて、環境や資源、循環、開発という4つの分野を総合的に学べることが大きな特徴で、多面的な視点で地球規模の課題にアプローチできます。たとえば私が取り組んでいるジオポリマー研究も、廃棄物の再利用による資源循環と最終廃棄物の減容、コンクリートに代わる新たな建設用原材料の開発という二つの目標を同時に追求しています。
また、この学科には「明確にやりたい研究が決まっている人」だけでなく、「漠然と環境問題に興味がある人」も多く集まります。私自身も最初からジオポリマーに専心していたわけではなく、入学後に多様な講義や実験を通じて徐々に興味の方向性が定まりました。学科内には多彩な研究室がありますから、一つひとつ覗いてみるうちに「これだ!」と思えるテーマに必ず出会えるはずです。環境資源工学科は好奇心や探究心を大いに刺激してくれる場所だと思います。
自分の研究に誇りを持ち、それぞれの領域を探求する
Q. 所属している山﨑研究室の特徴について教えてください。
山﨑研究室では、未利用資源や再利用資源の用途開発をテーマに研究しています。企業や研究所との共同研究も多く、ゼミ生一人ひとりが異なる領域を扱っていることも特徴です。そのため、日々の交流のなかで自分の専門外の知識に触れたり、異なる視点からの意見をもらえたりと、学びの機会にあふれています。ゼミ生は皆、自身の研究に誇りを持ち、丁寧に教えてくれるので、自然と活発な交流が生まれています。
山﨑先生も、広範な知識と的確なアドバイスでそれぞれの研究を支えてくださる一方、気さくで親しみやすいお人柄で、就職活動など研究以外の相談にも真摯に対応してくださいます。研究の深さと温かい雰囲気が両立した、非常に魅力的な研究室です。
Q. 就職活動について、どのような方針で臨まれましたか?
当初は材料系の企業を中心に考えていましたが、研究を通じて得た「より広範な社会貢献に携わりたい」という思いから、IT系企業に興味を持つようになりました。
就活でも研究で得た強みが生かされています。チームでコミュニケーションを取りながら、難しさを乗り越え遂行する力が養えたと思います。また、出てきた結果に対して、多角的かつ論理的に考えられるようにもなりました。
将来は、省エネや環境を絡めたインフラを支えるシステム開発など、社会基盤に関わる仕事を通じて、広く社会に貢献したいですね。

